| コラム 「食品開発×SDGs」 | ||
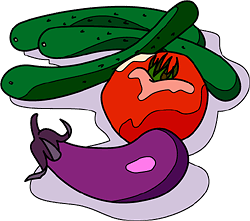 |
| コラム 「食品開発×SDGs」 | ||
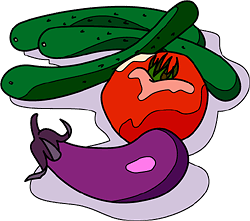 |
| (3) サスティナブルな食品の基準 | ||
|
皆さま、こんにちは。株式会社Agritureの小島です。
これまでのコラムでは、食品ロスを資源として捉える視点や、Z世代を中心としたサステナブル消費の動向についてご紹介しました。その中で、「サステナブルな食品をつくるには、必ず規格外原料や植物性食品といった特殊な素材を使わなければならないのか?」という疑問を持たれた方もいらっしゃるかと思います。今回はその問いに答える形で、食品メーカーが意識すべき「サスティナブルな食品の基準」について整理してみます。
サスティナブルな食品の基本的な考え方
食品業界におけるサステナビリティは、単に「環境にやさしい」ことだけを意味するわけではありません。国連のSDGs(持続可能な開発目標)に示されている通り、環境・社会・経済の3側面をバランスよく考えることが求められます。食品は人々の暮らしと文化に深く結びついた産業であるため、この3つの視点が同時に成立して初めて「持続可能」と言えるのです。
● 環境面:製造時のCO₂排出削減、フードロスの削減、リサイクル可能な包装の採用など
● 社会面:生産者の適正な労働環境やフェアトレードへの配慮、食品安全への責任
● 経済面:継続的に事業を回せるコスト構造や、地域との共生による経済循環
こう聞くと「自分たちにはハードルが高いのでは」と思われるかもしれませんが、サステナブルな食品づくりは必ずしも特別な原料や大掛かりな仕組みが必要なわけではありません。
サスティナブルの基準は簡単
たとえばチョコレートの場合、原料のカカオが規格外である必要はなく、生産者から適正な価格で買い取ること自体がサステナブルと言えます。あるいは、既に最終製品としてできたチョコレートを仕入れている場合であっても、販売した売上が奨学金や地域インフラ整備に還元される仕組みであれば、それも立派なサステナブルな取り組みです。
極論すれば、食品メーカーがしっかりと事業として販売数を伸ばし、売上を上げること自体が生産者の収益向上につながります。その循環が継続すれば、生産者は農業を続けられ、消費者には安定的に商品が届く。これもサステナビリティの重要な形のひとつです。
つまり大切なのは「完璧を目指すこと」ではなく、自社が取り組める範囲でより良い選択を積み重ねることです。包装を少し工夫する、余剰原料を別の商品に活かす、地元で採れた農産物を優先的に仕入れるといった小さな改善も、十分にサステナブルな食品につながっていきます。
加えて忘れてはならないのは、その取り組みをどう伝えるかです。せっかく良い実践をしていても消費者や取引先に理解されなければ広がりません。パッケージや商品ページに「なぜその選択をしているのか」を一言添えるだけで、消費者は共感し、企業価値は高まります。
御社の事業はサスティナブルですか?
OEMの依頼をする企業・個人の中で、「御社の事業はサスティナブルですか?」といった質問があるかもしれません。例えば、
● 製造工程でフードロス削減に取り組んでいるか
● 包装資材は環境に配慮したものを調達できるか
● 規格外農産物や地域原料の活用ができるか
といった点は、単なる付加価値ではなく、商品選定や取引判断の基準になりつつあります。
OEMで商品開発を考える際、依頼する側も「サステナブルな要素を何か一つでも商品に組み込みたい」と思うケースは少なくありません。原料・加工・資材のいずれかにサステナブルな要素を取り入れるだけで、他社との差別化につながり、提案の幅が広がる可能性があります。
特にZ世代をターゲットにした商品や、企業のCSR方針に沿った企画では、製造コストよりもサステナビリティへの姿勢を重視する傾向が強まっています。
つまり、OEMメーカーにとってサステナブルは「取り組めたら良い」ものではなく、取引先から選ばれるための前提条件になりつつあるのです。依頼側は「どのOEMメーカーが安いか」ではなく、「どのOEMメーカーとなら自社のサステナブル方針を実現できるか」で判断する時代が近づいています。
まとめ
OEMメーカーにとって、サステナブルはもはや「差別化の要素」ではなく、「依頼されるための前提条件」になりつつあります。依頼企業は価格や納期だけでなく、環境配慮・原料活用・地域性といったサステナブルな姿勢を見ています。
だからこそOEMメーカーは、製造工程や資材選定の工夫を積み重ねるだけでなく、それを明確に発信することが必要です。取り組みが小さな一歩であっても、依頼側からは「選びやすい理由」になり得ます。
OEM市場における競争力は、単なる製造能力から「どのような価値観で食品づくりを支えているか」へと移行しています。サステナブルを意識した取り組みを自社の強みとして整理し、商談の場で語れるようにすることが、これからのOEMメーカーに求められる姿勢です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
株式会社Agriture HP : https://agriture.jp/
Agritureの取り組むサスティナビリティについて : https://agriture.jp/sustainable/
|